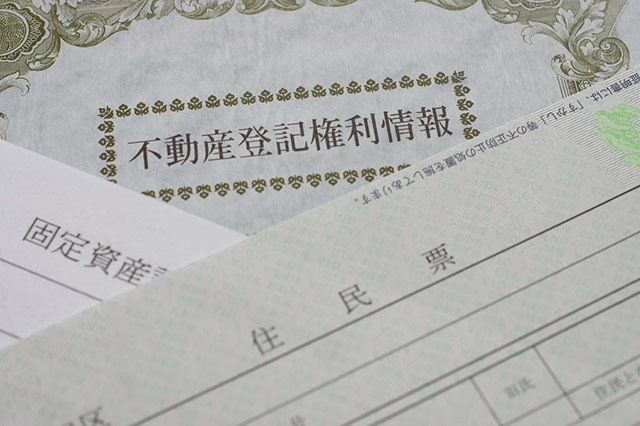分筆費用は誰が払う?ケース別に費用負担の考え方をご紹介
こんにちは!栃木県・地域専門の不動産売買専門店「イエステーション」の土屋です。
「土地を分筆したいけれど、費用は誰が負担するのだろう」
「相続で土地を分けたいが、分筆費用の支払いはどうしたら良いの?」
「かかる費用の目安はどれくらい?」
このような疑問をお持ちではありませんか?
土地の分筆には相応の費用がかかるため、誰が負担するのかを事前に確認しておくことが大切です。
今回は、分筆費用を誰が負担するのかについて、具体的なケース別に考え方を解説します。
さらに、分筆をスムーズに進めるための注意点もご紹介しますので、ぜひ参考にしてください。

分筆とは?分筆費用の内訳・相場も紹介
分筆(ぶんぴつ)とは、1筆(いっぴつ)と呼ばれる土地を、登記簿上で複数の筆に分割することをいいます。
分筆が必要になるケース例は、次の通りです。
- 相続:複数の相続人で土地を分けたい場合
- 売却:土地の一部だけを売却したい場合
- 贈与:土地の一部を家族や親族に贈与する場合
- 建築計画:用途に応じて敷地を区分けしたい場合(例:一部を駐車場として切り離すなど)
分筆手続きの一般的な流れ
分筆の手続きは専門知識と正確な測量が求められるため、ほとんどの場合、土地家屋調査士に依頼します。
一般的な手順は次の通りです。
- 土地家屋調査士へ依頼
- 土地家屋調査士が、法務局・役所で資料を収集
- 現地調査と境界確認
- 境界確定測量の実施と境界標設置
- 分筆登記の申請
まず、法務局や役所で地積測量図や公図などの資料を収集し、既存の境界情報を確認します。
その上で現況を調査し、隣地所有者との立ち会い・境界確認の日程を調整して、測量に必要な準備を整えます。
既存資料だけでは境界が確定できない場合は、正確な測量(確定測量)を行い、必要に応じて境界標を設置して境界位置を明らかにする対応を取ります。
最後に、測量結果を基に分筆登記手続きを進める流れです。
土地の測量については「土地の売却で測量は義務?必要なケースや費用・流れを解説!」で詳しく解説しています。
分筆にかかる費用の内訳と相場
土地家屋調査士に分筆を依頼した場合、主な費用と目安は次の通りです。
【登記申請費用】
- 登録免許税:分筆後の土地1筆につき1,000円(例:1筆を2筆に分ける場合: 2,000円)
- 必要書類の取得費用:登記事項証明書や住民票など、1通につき数百円
【土地家屋調査士への報酬(測量費用も含む)】
- 登記申請のみ:5万円~
- 隣地境界がすでに確定している場合:約10万円~
- 境界が未確定の場合(確定測量あり):約40万円~
分筆費用は、土地の面積・形状、隣地所有者の協力度、隣地立ち合いの有無によっても大きく変わり、場合によっては数百万円以上かかることもあります。
境界が明確で形状が単純な土地では費用を抑えやすい一方、都市部で形状が複雑な土地や隣地所有者が多い土地では測量の工程が増えるため、費用が高くなる傾向があります。
分筆費用の詳しい内訳、必要な書類などについては、「土地を分筆して売却するには?費用や注意点もチェック!」で詳しく解説していますので、ぜひあわせてご参照ください。
分筆費用は誰が払う?ケース別に費用負担の考え方をご紹介
分筆費用を誰が負担するかについて、法律で明確に定められたルールはありません。
実務では、分筆によって利益を受ける当事者が負担する、あるいは関係者間の協議で合意した方法を採用するのが一般的です。
そのため、代表的なケースと費用負担の考え方を参考にしつつ、当事者同士で早めに話し合うことが重要です。
相続で分筆する場合
相続時の分筆費用は、次のような負担方法が考えられます。
- 相続人全員で負担:取得面積に応じて費用を分ける
- 特定の相続人が負担:特定の土地を取得する相続人だけが負担する
- 相続財産全体から負担:相続財産の現金や預金から分筆費用を支出する
どの方法を選ぶかは遺産分割協議で決定します。
売却目的で分筆する場合
売却を目的に分筆する際は、一般的に売主が負担することが多いです。
しかし、買主の要望によって分筆する場合や、双方にメリットがある場合は、買主が全額負担したり、売主と折半したりするケースもあります。
隣地との境界確定が必要な場合
地域の慣習や隣地所有者の考え方によって対応は異なりますが、隣地との境界が未確定で、その確定が分筆に不可欠な場合、隣地所有者との協議によって費用を折半することがあります。
隣地側も境界が明確になるメリットを得られるためです。
費用負担の取り決め方
費用負担を巡る争いを防ぐには、事前の話し合いと書面での合意が不可欠です。
- メリットを受ける側を客観的に評価する
- 負担割合や支払い時期を明確にする
- 契約書や遺産分割協議書など、正式な書面に記録する
これらを徹底することで、分筆後の関係悪化や追加費用を巡るトラブルを避けられます。
土地の分筆をスムーズに進めるための注意点と準備

土地の分筆をスムーズに進めるため、注意点や準備のポイントも確認しておきましょう。
分筆できないケースがあることに注意
土地の分筆は、常に自由に行えるわけではありません。
以下の条件を満たさない場合、分筆できない、あるいは分筆しても建築ができない可能性があります。
①分筆後の面積が0.01㎡/最低敷地面積を下回る場合
分筆後の面積が0.01㎡未満の土地は、登記簿に正しく記載できないため、分筆登記が認められません(不動産登記規則第100条)。
また、市区町村の都市計画や地区計画で住宅用地の最低敷地面積が定められている場合、その基準を下回る分筆を行うと建築が許可されないなど、利用制限を受けることがあります。
②接道義務を満たさない場合
建築基準法上、建物を建てるには原則として幅4m以上の道路に2m以上接している必要があります(建築基準法第42条・第43条)。
分筆によってこの接道義務を満たさない土地が生じる場合、建築確認が下りず、実用的に分筆が難しくなる可能性があります。
接道義務については「接道義務とは?違反になるケースや例外についても解説」で詳しく解説しています。
③分筆が不合理であるとされる場合
土地の分割方法が不合理と判断される場合も、分筆登記が認められないことがあります。
例えば、宅地として利用できない形状に細分化することや、固定資産税評価額を意図的に下げる目的で不自然な分割を行うケースなどがあるでしょう。
不合理な分割は、適正な土地利用や税制の公平性を損なうため、法務局で申請を却下される可能性があります。
④境界確定ができない場合
隣地所有者の立ち会いが得られない、または所在不明で境界が確定できない場合には、「筆界特定制度」などを利用して、境界を明確にすることが求められます。
詳しくは、法務省の「筆界特定制度」をご確認ください。
費用負担でトラブルになりやすい事例
分筆費用の負担を巡っては、以下のようなトラブルが発生しやすいので注意が必要です。
- 相続時:相続人の一部が費用負担を拒否し、協議が長期化する
- 売買時:売買成立後に分筆費用を請求され、「誰が払うか」を巡って揉める
- 追加費用:境界確定測量が予想以上に複雑で、当初の見積もりを超える金額が発生する
これらを避けるためには、手続きを始める前に負担者と支払い方法を明確に決め、書面で合意を残すことが重要です。
分筆を進める前におすすめしたい準備
トラブルを回避し、手続きをスムーズに行うには、事前の準備が欠かせません。
①専門家に相談する
分筆は測量・登記・境界調整など専門的な知識が必要です。
土地家屋調査士に依頼すると、正確な測量や書類作成が可能で、トラブルを防げます。
相続や売却が絡む場合は、不動産会社や司法書士に早めに相談すると安心です。
②見積もりと負担割合を確認する
複数の調査士に相見積もりを取り、費用項目と総額を把握しておきましょう。
あわせて、追加費用の可能性がないか、あるとすればどれくらいの費用がかかりそうか、予想額も確認しておくと、不測の出費に慌てずに済みます。
③手続き期間とスケジュールを把握する
境界立ち会いや法務局の処理には時間がかかることがあります。
売買や建築の計画がある場合は、余裕を持ってスケジュールを立てることが大切です。
④隣地所有者との調整を早めに行う
立ち会いや境界確認には、隣地所有者の理解と協力が不可欠です。
事前説明を丁寧に行い、円滑に立ち会いが進むように配慮しましょう。
地域によっては、慣習として数千円から1万円程度の立ち会い調整のための謝礼が必要になるケースもあるので、土地家屋調査士に確認し、準備しておくとスムーズです。
分筆費用を誰が払うかはケースによる。事前の取り決めがおすすめ
分筆費用には、登録免許税、測量費用、土地家屋調査士への報酬などがあり、数万円から数百万円以上と幅があります。
土地の形状や面積、境界確定の有無などの条件によって、大きく変動するからです。
分筆費用を誰が負担するかについて法的な決まりはありません。
相続では相続人同士の協議で決める、売却では売主・買主間の合意で決めるのが一般的です。
費用負担や支払い時期は早めに話し合い、書面で合意しておくことがトラブル防止の鍵となります。
分筆は測量や登記など専門知識を要する手続きです。
土地家屋調査士に依頼することで、正確かつ円滑に進められます。
相談の際は、見積もり内容・負担割合・手続き期間を事前に確認しておくと安心です。
土地の分筆の際、相続や売却が絡む場合は、不動産会社や司法書士に早めに相談することをおすすめします。
栃木県で不動産の売却を検討している方は、栃木県・地域専門の不動産売買専門店「イエステーション」に、ぜひご相談ください。

宇都宮店 土屋 清
売却の際には購入の時とはまた違った不安があると思います。自分の希望価格で売れるのか・・・問題は発生しないか・・・不安は尽きません。安心・安全のお取引をモットーとしておりますので、しっかりとお客様の状況をふまえ、万全の体制でサポートさせて頂きます。
その他の不動産売却の基礎知識