不動産の相続登記をしないとどうなる?4つのリスクを解説
こんにちは。栃木県・地域専門の不動産売買専門店「イエステーション」の土屋です。
「不動産を相続したけれど、相続登記はどうすれば良いのだろう?」
「手続きが面倒で、ついつい後回しにしてしまっている...」
「相続登記をしないと、どんなリスクがあるのだろう?」
こんな不安や疑問をお持ちではありませんか?
実は、2024年(令和6年)4月から相続登記が義務化され、正当な理由なく手続きを怠ると、罰則(過料)の対象となる可能性があります。
さらに、相続登記をしないことで、不動産の売却ができなくなったり、将来的に大きなトラブルに発展したりするリスクもあるのです。
今回は、不動産の相続登記をしないとどうなるのか、その疑問についてお答えします。
相続登記の義務化の背景や、相続登記をしないことで起こる具体的なリスクと対策についても詳しく解説していきます。

不動産の相続登記とは?義務化の背景から知ろう
不動産の相続登記とは、亡くなった方が所有していた土地や建物の名義を、相続人の名義に変更する手続きのことです。
正式には「相続による所有権移転登記」と呼ばれ、法務局で行います。
これまでは、相続登記をするかどうかは相続人の判断に任されていました。
しかし、2024年(令和6年)4月1日からは、相続によって不動産を取得したことを知った日から「3年以内」に登記申請することが法律で義務付けられました。
なぜ、このように義務化されたのでしょうか?
背景にあるのは、「所有者不明土地」の増加という深刻な社会問題です。
所有者不明土地とは、例えば、相続登記をせずに放置された土地では、登記簿を見ても現在の所有者が誰なのかわからず、活用や売買ができない状態になっている土地のことを指します。
また、所有者がわかっていても、連絡がつかないケースもあります。
こうした土地は全国で増え続けており、公共事業の妨げになったり、空き家の放置による防災上のリスクを生んだりと、地域社会にも大きな影響を及ぼしています。
この問題を解消するために、相続登記の義務化が導入されました。
「相続した人がきちんと登記をしておく」ことが、不動産の流通を円滑にし、トラブルを未然に防ぐ重要なステップとなるのです。
なお、登記をせずに放置した場合には、罰則(過料)が科される可能性もあります。
詳しくは次のブロックでご紹介しますね。
不動産の相続登記をしないとどうなる?4つのリスクを確認
「手続きが面倒だから」「とりあえず放置しても困らないのでは?」
そう思って相続登記を先延ばしにしている方もいるかもしれません。
しかし、登記をしないまま放置しておくと、後から取り返しのつかないトラブルや負担が発生するリスクがあります。
ここでは、代表的な4つのリスクをご紹介します。
1. 罰則(過料)の対象になる
2024年4月から相続登記は法律上の義務となり、正当な理由なく、相続した不動産について3年以内に登記を行わなかった場合、10万円以下の過料が科される可能性があります。
「戸籍収集に時間がかかった」「相続人が多く、協議がまとまらなかった」など、事情によっては考慮される場合もありますが、ほとんど認められないと思っていたほうが良いでしょう。
そのため、単に「忙しかった」「面倒だった」といった理由では認められません。
罰則の対象とならないためにも、早めの対応が重要です。
2. 不動産の売却や担保設定ができなくなる
相続登記をしていない不動産は、名義が亡くなった方のままであるため、相続人がその不動産の所有権を第三者に主張できません。
つまり、たとえ実質的に不動産を管理している立場であっても、売却や担保設定などの法的な手続きが一切できない状態です。
急に資金が必要になった場合でも、登記が済んでいないと買い主も金融機関も対応できず、機会損失につながるおそれがあります。
3. 相続関係が複雑化し、相続人が増える・親族間のトラブルに発展する可能性がある
相続登記をせずに放置していると、相続人の死亡や代替わりによって登記に関与すべき人が増え、相続関係が複雑化します。
例えば、ある相続人が亡くなれば、その子どもが新たな相続人となり、権利関係がどんどん枝分かれしていきます。
その結果、書類集めも困難になり、遺産分割協議が成立しにくくなるなど、手続きが大幅に遅れてしまう原因になるのです。
また、「誰がどの権利を持つか不明確」な状態が長引くことで、親族間の不信感や争いが生じるリスクも高まります。
「勝手に使われていた」「修繕費を誰が払うかでもめた」など、さまざまなトラブルに発展してしまう可能性があるのです。
4. 不測の管理責任や損害賠償リスクを負うことがある
登記が済んでいないからといって、管理責任がなくなるわけではありません。
相続人が実際に不動産を使用・管理している場合、その人に責任が及ぶ可能性があります。
例えば、空き家が劣化して瓦が落下し、通行人にケガを負わせた場合などは、損害賠償を求められるケースも実際に起きています。
さらに、管理されない空き家は自治体から「特定空き家」に指定され、「固定資産税の住宅用地特例」が解除されることも。
その結果、固定資産税が最大で6倍、都市計画税は最大で3倍に跳ね上がるという金銭的リスクもあります。
特定空き家については「特定空き家とは?指定されるケースや罰則をチェック!」で詳しくお伝えしていますので、あわせてご覧ください。
固定資産税の扱いや義務化の詳細を知りたい方は、こちらのコラムで詳しく解説しています。
相続登記しない場合は固定資産税を誰が支払う?申請の義務化はいつ?
不動産の相続登記を放置しないためにできることは?3つのステップをご紹介
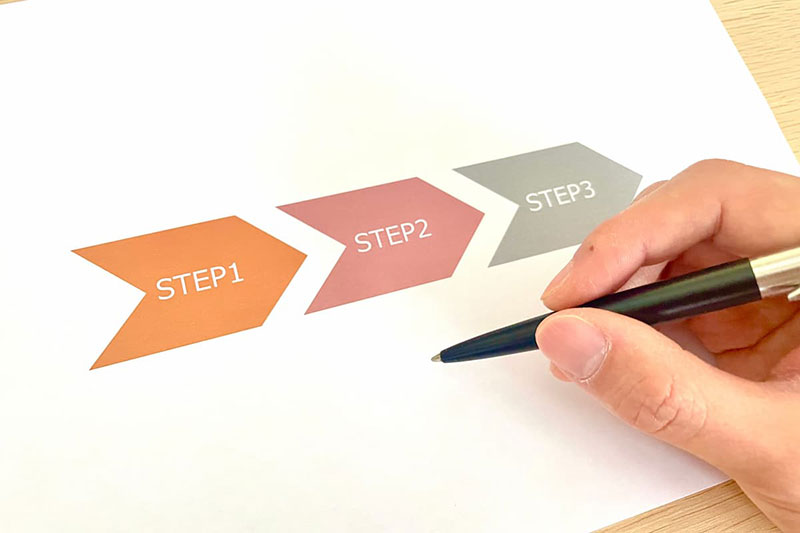
「相続登記が必要なのはわかったけれど、実際には何から始めれば良いのだろう?」
そんな不安を抱く方も多いのではないでしょうか。
相続登記は、主に以下の3つのステップで進めるのが一般的です。
流れを理解しておくことで、スムーズな手続きにつながります。
ステップ①相続人を確定する
まずは、相続人が誰なのかを確定する必要があります。
このために必要なのが、「被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本一式」と、「相続人全員の現在の戸籍謄本」です。
これらの書類をもとに、法定相続人を証明します。
なお、相続人が複数いる場合には、遺産分割協議が必要になるケースもあります。
ステップ②必要書類を準備する
相続登記に必要な書類と、取得費用の目安は以下の通りです。
- 被相続人の戸籍謄本・除籍謄本(出生から死亡まで):450円程度/通(除籍謄本・改製原戸籍の場合は750円程度/通)
- 被相続人の住民票の除票 または 戸籍の附票:300円程度/通
- 相続人全員の戸籍謄本:450円程度/通
- 相続人の住民票(申請者分):300円程度/通
- 登記事項証明書(登記簿謄本):600円程度/通
- 固定資産評価証明書:300円程度/通
相続人の人数や戸籍の改製・転籍の有無により、通数や費用は変動しますが、相続登記に必要な書類の取得費用は、最低でも3,500円程度はかかると見ておきましょう。
また、状況に応じて、下記の書類が必要な場合もあります。
- 遺産分割協議書:複数の相続人がいて、遺産の分け方について話し合った場合
- 相続人全員の印鑑証明書(300円/通):遺産分割協議書を作成した場合に添付
- 遺言書(自筆証書・公正証書など)被相続人が遺言を残していた場合
必要書類について詳しく知りたい方はぜひ「相続登記の必要書類をケースごとにご紹介!登記方法や費用面も解説」もご参照ください。
ステップ③法務局で登記申請を行う
書類がそろったら、被相続人の不動産を管轄する法務局で登記の申請を行います。
この際、登録免許税がかかります。
相続登記における登録免許税は、対象不動産の「固定資産評価額の0.4%」が基本です。
例えば、評価額が1,000万円の不動産であれば、登録免許税は4万円となります。
手続きをご自身で行うのが不安な場合や、相続人が多数いて複雑なケースでは、司法書士に依頼する方法もあります。
司法書士に依頼した場合、上記の登録免許税に加えて、5〜10万円程度の報酬が必要となります。
依頼する際は、事前に見積もりを取り、サービス内容や費用をよく確認してから判断すると安心です。
不動産の相続登記はリスク回避のために早めの手続きを
相続登記をしないまま放置すると、不動産の売却ができない、損害賠償を請求されるおそれがあるなど、さまざまなトラブルにつながります。
2024年4月からは登記の申請が義務となり、正当な理由なく怠った場合には10万円以下の過料が科される可能性もあります。
相続登記をしないと相続関係が複雑化して手続きが進まなくなったり、担保設定ができなかったりと、不動産の活用を妨げる大きな障害になります。
相続登記の手続きは、「①相続人の確定」「②必要書類の準備」「③法務局での申請」という3ステップで進めるのが基本です。
将来的に不動産の売却や有効活用を考えているなら、相続登記を早めに済ませておくことが望ましいでしょう。
栃木県で不動産の売却を検討している方は、栃木県・地域専門の不動産売買専門店「イエステーション」に、ぜひご相談ください。

宇都宮店 土屋 清
売却の際には購入の時とはまた違った不安があると思います。自分の希望価格で売れるのか・・・問題は発生しないか・・・不安は尽きません。安心・安全のお取引をモットーとしておりますので、しっかりとお客様の状況をふまえ、万全の体制でサポートさせて頂きます。
その他の不動産売却の基礎知識










